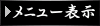[HOME] >
[神社記憶] >
[甲信越地方] > [HOME] >
[神社記憶] >
[甲信越地方] >
|
|
|
金櫻神社
かなざくらじんじゃ
山梨県山梨市牧丘町杣口2919

|
||
山梨県山梨市(旧牧丘町)にある。杣口という場所。
「杣」とは、木材をとる山、あるいはキコリのこと。
杣口は、金峰山(2599m)への入口ということ。
塩山駅から金峰山方面(北西)へ8Kmほど。
牧丘の中心部からも5Km。
道路を走っていると、道路右側に、朱の鳥居と社号標があり、
旧参道と思われる道が道路横から続いていたが、
そこから数100m、道路を走ると境内入口(道路右側)に到着。
入口の鳥居をくぐり、しばらく暗い道を歩くと、
お寺の裏側に出るが、そこが境内。
木々の茂った参道の先に、社殿が鎮座している。
金峰山を神体山とする神社で、里宮の一つ。
社記によると、仁寿3年(853)3月、天台宗智証大師により
大和国から勧請したという。
旧社地は、金峰山東登山道の御料林内にあり、
石積や礎石、古代文字を刻む石碑などが残っているらしく、
町の史跡になっているらしい。
参拝時には、このことを知らなかったので、
訪問していないのが、残念。
(後日訪問したので、下に追記した)
静かで、寂びた神社。
本殿の右後方に神木らしき立派な木に注連縄が張られていた。
社殿内の幕には「桐紋」が付いていたが、
拝殿・本殿には金の文字。
社名から付けられた紋章だろう。と思う。
参道の鳥居と社号標  | 境内入口  |
境内 |
 |
社殿  | 社殿  |
本殿  | 御神木  |
|
由緒 大字杣口にあり、地名を小倉山米沢という。金桜神社は金峰山の里宮にて古くは大社なりと伝う。大国主命、少彦名命を祭神とし、蔵王権現および小守勝手の両祠を併祀す。神社の創立は明らかではないが、社記によると、仁寿3年(853)3月天台宗智証大師により大和国より勧請した鎮守社という、旧社地は高原といい、金峰山東登山道の御料林内にあり、往古の石積や礎石、古代文字を刻む石碑などが残されている。町指定の史跡である。 平安以降は山岳信仰と密教の修験道場の聖地とされ、甲斐国志に「此所ヨリ南方富士路黒駒ニ達スルヲ道者海道ト云フ」と記されている。現在の社地は正徳2年(1712)に遷座されたものである。本殿は一間社唐破風付向拝にて屋根は銅板葺入母屋造りで箱棟に千木をのせる。身舎は円柱にて前部と後部に分かれ、正面に開扉がある。高欄付縁を四方にめぐらし、木造彫刻の狗犬は古く、その伝説が残されている。 神社の例祭は毎年4月11日に行われ、神輿番は宮本の(杣口、大室、山本)(城古寺、請地)(隼)(窪平、替地、堀ノ内、琴川)(千野々宮)の五地区に分かれている。また、杣口の打ちはやしは上杣口、下杣口の二座があり、5年に一度の宮本当番のとき交互に行なわれる。町指定の民族文化財となり。祭礼は隼の地蔵尊まで末社21、行程28㎞御幸する −『平成祭データ』− |
後日、旧社地である奥社地跡を訪れてみたので追記。
奥社地跡の位置は、当社から219号線を北へ2Kmほど。

右手に林道への入口がある分岐点に案内板が立っており、
その案内板の背後の林の奥にある。
219号線から少し山道を上ると赤い鳥居が立っており、
道がないので、とにかく上を目指して進むと石垣跡らしいものがある。
昔は、そこに社殿があったのだろう。その後方の斜面をさらに上ると
人工物らしき立石があり、さらに突き当たるまで上ると、祠が祀られている。
林道分岐点に案内板、右手が林道  | 奥社跡入口  |
鳥居が立っている |
 |
鳥居  | 山道を進む  |
石垣跡 |
 |
さらに参道  | さらに参道  |
突き当たりに祠 |
 |
祠  | 祠  |
|
金桜神社奥社地跡
町指定文化財
金桜神社は仁寿三年(八五三)大和国より勧請米沢山大禅寺の鎮社
なり、この地を高天が原と称し山岳信仰と密教との修験道城の聖地と
した頃は金峯山東登山道の里宮として栄えた。昭和五十一年三月三十日 ここより黒駒に達する道を道者街道という。天正十年(一五八二)織 田軍の兵火に遭い、社殿等焼失す。以後里宮は二本松を経て正徳二年 (一七一二)に今の地に移る。奥社地には往時の石垣、建物の礎石、 古代文字の碑が残され、附近には東谷、西谷、青山千坊、護摩坂、堂 の上、大門くだりなど社人、社僧の実権を偲ぶ史跡を存す。 −案内板より− |