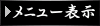[HOME] >
[神社記憶] >
[関西地方] > [HOME] >
[神社記憶] >
[関西地方] >
|
|
|
三宅神社
みやけじんじゃ
京都府亀岡市三宅町121

|
|
京都府亀岡市にある。
亀岡駅の南東1Kmほどの三宅町に鎮座。
年谷川の北側、402号線から少し南へ入った場所に境内がある。
境内入口は東向き。
社前に小さな石橋があり「式内三宅神社」と刻まれた社号標が建っている。
鳥居をくぐり境内に入ると、正面に社殿。
社殿の前にも鳥居が建っている。
拝殿は無く、本殿に上屋が(覆い屋根)が設置された簡素な構造。
境内左手に神楽殿らしき舞台があり、境内右手には赤い稲荷社。
その奥、本殿の右手には豊受大神が祀られている。
今はこんなに小さな神社だが、
かつては一町四方(100m四方)の社域だったらしい。
参拝は炎天下の真夏の休日。
創祀年代は不詳。
安閑天皇二年五月屯倉(みやけ)に併設されたと伝えられ、
式内社・三宅神社に比定される古社。
食物を保存する倉だったためか
叢稲荷、 草分稲荷、三宅稲荷などとも呼ばれ崇敬された神社。
天正の戦乱や寛文の火災で焼失し
延宝元年、城主の松平忠明によって再建。
代々城主の祈願所となった。
明治六年村社に列した。
境内入口  | 境内  |
神楽殿  | 社殿  |
本殿 |
 |
稲荷社  | 豊受大神  |
|
三宅神社
当社の創祀は不明ですが、古代大
和朝廷の直轄地として経済的基盤
となった屯倉に由来する神社で、平
安時代の書物「延喜式神名帳」にも
丹波国桑田郡十九社の内の三番社
として記載された古社です。叢稲荷、
草分稲荷、三宅稲荷とも呼ばれ、往
古は一町四方の広大な社地を有し
ていましたが、天正の兵乱や寛文三
年(一六六三)等度重なる火災によ
り徐々に社域も小さくなっていき
ました。かつての社域の一部は、稲
荷垣内との地名も残されています。社は延宝元年(一六七三)に建て られ、その後元禄十一年(一六九八) に上屋が再建されました。また旧領 主代々の祈願所でもありました。 祭神は穀物の神である倉稲魂命、 稚産霊命、豊保食命の三柱が祀られ ています。 −境内案内板− 郡家と三宅
屯倉(みやけ)というのは大化改新以前に存在した
天皇の直轄地をさしており「日本書紀」安閑天皇二年の条
をみると、丹波国蘇斯岐(そしき)の屯倉がおかれたことが記され
この(みやけ)がごこに置かれたかについては諸説がある。郡家(ぐんけ)を古く「こおりのみやけ」と読み郡衛ともいった。 郡家は今日の郡の役所と考えられ、その役所には郡庁、 官舎、厨家、廐のほか十数宇の正倉が建ち郡の政治、経 済の中心となった。三宅郡家説を主張する理由 としては、旧山陰道の要地を占め、郡家面積 としても河岸段上、方二町の平坦面がらく らくとその中におさまり、式内社三宅神社 (俗に三宅稲荷)は屯倉の存在を物語るものと して古くから注目されてきた。 最近郡家の発掘報告が次々ちなされ、 次第にそのアウトラインが浮び上ってきたので、 ここ三宅の地にもやがて科学的な調査の 日が近づくことも時間の問題といえよう。 −境内案内板− 創立年代不詳。ただし、安閑天皇2年5月屯倉に併設されたとしている。天正の戦乱で焼失した。延寶元年に城主の松平忠明が再建。代々城主の祈願所となり、多くの崇敬者が参拝した。明治6年村社。明治40年指定村社となる。 −『平成祭データ』− |
【 三宅神社 (亀岡市)(印刷用ページ) 】