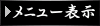[HOME] >
[神社記憶] >
[北陸地方] > [HOME] >
[神社記憶] >
[北陸地方] >
|
|
|
神明社
しんめいしゃ
福井県鯖江市水落町81

|
||
|
式内社 越前國今立郡 岡本神社 |
福井県鯖江市にある。
福井鉄道福武線・神明駅の南東、すぐ近くの水落に鎮座。
周囲の道路から境内へ入れるが、表参道は南側。
ということで、南側の参道入口から参拝開始。
参拝日は、小雨の降る5月の連休の午後。
参道入口には神明造の石鳥居。
鳥居をくぐると鬱蒼と木々の茂る200m近い参道。
参道を歩くと右手には烏ケ森の社叢が広がっている。
しばらく歩くと右手の月形の池の側に「慶長の燈籠」。
この池では雨乞い神事が行われていたという。
さらに歩くと社殿のある境内だが、
左手に小さな古墳があり、古墳の上に神符納蔵。
境内中央に拝殿があり、拝殿の後方、中雀門の奥に本殿がある。
本殿の屋根は銅板で覆われているが肉厚で、
ひょっとすると銅板の下は茅葺なのかもしれない。
社伝によると、
安康天皇の御代の勧請という。
『明治神社誌料』によると、当社を式内社・岡太神社とする説があるらしい。
往古は、現在地から北東3Kmほどにある文殊山の南麓、
現下河端町の「湯の花」に鎮座していたが
鳥羽天皇の大治四年(1129)五月十五日、
当国押領使(兼神領使)藤原国貞の神託により
烏ケ森の現在地に遷座。
その後、朝倉家より田地一段歩が寄付、
太閤検地の際、田地三段歩が寄付されるなど
歴代国主により庇護された神社。
口碑によると、
慶長六年(1601)松平秀康公入国の際、
水落烏ケ森にさしかかると乗馬がいななき
物怖れをして進まず、臣下に偵察させたところ
森の中に立派な神社が鎮まっているのを知り、
下馬して社殿に額ずき、御高五十石を献じたという。
また、松平秀康公の娘の病気平癒を祈願したところ
全快したので、社殿および神官瓜生家の家を寄進したとも。
本殿垂木には「御志ろおひめさま御きしん」の金具が打たれているらしい。
明治八年五月県社に列せられ、
明治四十五年、観音寺にあった無格社天満宮を合祀した。
さて、『式内社調査報告』によると
越前国神名帳に「従四位 土輪神」とある
式内社・土輪神社の所在は不明としながらも、
当社境内の土宮が、土輪神社であるという説が紹介されている。
また、『明治神社誌料』では、
越前国神名帳に「従四位 平岡神」とある式内社・枚岡神社は、
境内末社の平岡八幡および多賀社だとする説があるようだ。
で、探してみたが土宮・八幡・多賀がどこにあるのかわからなかった。
当社境内には、金刀比羅宮、八幡神社、春日神社、
多賀神社、土宮の五境内社があるらしい。
金刀比羅宮は本殿後方に確認できる。
垣の中の本殿左右には境内社の祠が一つずつある。
広い境内なので他にも祠があるのかもしれないが
多賀宮・土宮は神明社と深い繋がりがあるので
本殿側の境内社のどちらかに祀られていると考えるのが妥当だと思う。
社殿の後方に金刀比羅宮があり、
境内左奥には、重要文化財の旧瓜生家が建っている。
境内には巴紋と付けた神馬像がある。
三巴紋が、当社の神紋なのだろう。
鳥居 |
 |
参道  | 慶長の燈籠  | 参道  |
境内 |
 |
神符納蔵 |
 |
拝殿  | 社殿  |
本殿  | 本殿  |
本殿左の境内社  | 本殿右の境内社  |
金刀比羅宮  | 神馬像  |
旧瓜生家 |
 |
|
鯖江市指定文化財
烏ケ森社叢
鯖江市指定文化財 神明社の神符納蔵
鯖江市指定文化財 神明社慶長の燈籠
−境内案内板− | |||||||||||||||||||||||