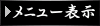[HOME] >
[神社記憶] >
[四国地方] > [HOME] >
[神社記憶] >
[四国地方] >
|
|
|
神野神社
かんのじんじゃ
香川県仲多度郡まんのう町神野168−2

|
||
香川県まんのう町にある。
JR塩入駅の北東2Kmほど。
満濃池の入口に鎮座している。
満濃池に面して階段があり、階段を登ると境内。
まんのう町最古という石造の鳥居と社殿しかない、
そんな感じの、ガランとした境内だったなぁ。
創祀年代は不詳。
一説には、推古天皇の御宇の造営。
大宝年間に、当地に井戸があり、天真名井と称して、
罔象女命を祀っていたが、満濃池が築成される時に、
堤の上に遷して池の守護神としたもの。
大同3年、池の破壊の時、
当社の北方に祀られていた加茂大明神を合祀。
弘仁年間、嵯峨天皇の勅により、空海が満濃池を修築したことにより、
その後、嵯峨天皇を奉斎。
当地は真野郷に属しているが、平安以前は神野郷であった。
平安時代、嵯峨天皇の御諱である神野(あるいは加美野)に触れるとして、
「神」の字を「真」に変更した。
境内社として、神櫛神社がある。
神櫛王命を祀り、東照宮を合祀している。
神紋は、社殿に付いていた三つ巴だと思う。
当社の主祭神を、応神天皇とする説もあり、
また、水神を祀っているので、多分、これで正しい。
社前の満濃池 |
 |
鳥居  | 社殿  |
境内から満濃池 |
 |
境内入口  | 本殿  | 社日と境内社  |
|
神野神社と鳥居
神野神社は、満濃池の守護神として奉斎され延喜式内
讃岐二十四社の一つにかぞえられた古社である。祭神は、天穂日命 水波能売命等四柱がある。 正治元年(一一九九)二月十二日矢原庄司義宗によって 再建以来、{寛永五年(一六二八)萬治二年(一六五九) 宝暦四年(一七五四)文化元年(一八〇四)文政三年(一八二〇) 明治三年(一八七〇)}等の池普請の度毎に社殿の造営が 行われ、昭和二十八年(一九五三)の満濃池拡大工事によって 現在地に遷座したものである。 社前の石造鳥居は、文明二年(一四七〇)の建造で、本町内 最古の鳥居である。 −社前案内板より− |
【 神野神社 (満濃池)(印刷用ページ) 】