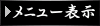[HOME] >
[神社記憶] >
[四国地方] > [HOME] >
[神社記憶] >
[四国地方] >
|
|
|
小野神社
おのじんじゃ
高知県南国市岡豊町小蓮字宮ノ前1189

|
|
式内社 土佐國長岡郡 小野神社 |
高知市との境に近い南国市、国分川の北にある。
高知医科大学の北。西へ2〜3Kmで土佐神社。
東へ2〜3Kmで国分寺、1Kmほど南東には、
豊岡上天神社がある。
32号線蒲原別交差点を北へ入ってすぐの所に鳥居があり、
丘の上が境内になっている。
階段を登ると、右へ曲がる地点にも鳥居。
さらに階段を上がると、また鳥居があり、すぐ拝殿。
昼でも暗めの境内で、夜は、ちょっと怖そうな感じだが。
創祀年代は不詳。
式内社・小野神社に比定される古社。
小野神社の社名は、小野氏の祖先を祀ると言われているが、
地名から来たとする説も有る。
さらに、豊岡神社が合祀されていることにより、
地元では豊岡大明神とも呼ばれ、
小野古城大明神との別称もある。
小野神社と豊岡神社が並立に建てられていた時期があり、
当時、豊岡神社の方が有名で、
小野神社を「若宮」と記したものもあるようだ。
合祀されている豊岡神社は、「門丸様」とよばれ、
「門丸様の石」というものがあり、
浄水をかけて雨乞いすると必ず降雨するという伝承がある。
しかし、祈雨の年には必ず変事が起るため、
廃止されたという。
その「門丸様の石」は未確認だ。
境内には2・3の境内社があり、式内社調査報告では、
若宮神社・佐波為神社とある。若宮神社は、当社に合祀された
豊岡神社の末社との説がある。
佐波為神社には野槌神社が合祀されている。
社頭 |
 |
鳥居扁額  | 参道の鳥居  |
参道の小祠  | 参道階段  | 上から  |
境内  | 拝殿  |
境内社  | 本殿  | 境内社 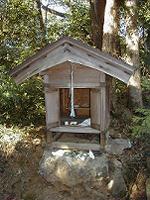 |
|
勧請年月や由来など不明だが、小野村の産土神
として信仰された。ところで当社鎮座の場所は中世小野城
のあったところで、長宗我部元親の二男親和が讃岐の香川
家をついだが、香川家の衰退により帰国し、元親から小野
の古城を与えられ小野村に住んだといふ。『南路志』に小
野神社について「豊岡大明神麻小野古城山」と記されたのもそのた
めである。小野神社と豊岡大明神を合祀したため混乱がお
こったことについては前記したが、時期は不明だが小野神
社と並列して建てられた豊岡大明神(豊岡神社)が有名にな
ったため、小野神社といへば豊岡大明神のことと思うよう
になり、中には両社を同一の神社と考える者もあらわれた
ようである。『南路志』には小野神社を「若宮本社脇」と記
し、脇宮・若宮としてあつかっている。ところで小野神社
の神体について『皆山集』に「式社記云、此社、小野村古
城址豊岡社東側ニ小社あり。是なり。束帯せる男体の木像
を以て神体とす。今其神像豊岡社ニ蔵む。古、何時豊岡社
に合するを知らす。」と記されてあり、神体すら豊岡神社に
おさめられては混乱するのもうなづけるのである。式内社
の小社で、明治五年社格制定にあたり村社となった。『長
宗我部地検帳』によれば、長宗我部氏の有力家臣小野民部
承は一反三三代の土居屋敷に住み、約二五町の給地をもっ
ているが、小野氏は中世において伝統的に小野村での豪族
としての地位を保っていたのであらう。小野神社のある南
には山麓に善楽寺があったが、検地の段階では阿弥陀堂が
残っている。豊岡大明神は社領八反四十八代四歩があった
が、長宗我部時代に取り上げられたと伝えられている(高
知県神社明細帳)。山内藩政時代は御山方の支配をうけ、棟
札に寛文四年(一六六四)三月、元緑十五年(一七○二)九
月、元文三年(一七三八)十一月のものがあり、修造された
が豊岡大明神と記されている。
−『式内社調査報告』− |
【 小野神社 (高知)(印刷用ページ) 】