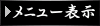[HOME] >
[神社記憶] >
[甲信越地方] > [HOME] >
[神社記憶] >
[甲信越地方] >
|
|
|
塩野神社
しおのじんじゃ
長野県上田市保野字塩野429

|
|||
長野県上田市にある。
上田から別所温泉へ向かう177号線(鹿教湯別所上田線)の保野。
塩田ゴルフセンターの南にある。177号線からは畑のむこう。
南面している境内入口には黄色く塗られた鳥居がある。珍しい。
境内には上田市指定文化財の廻り舞台もある。
保野は、上田から別所温泉へ向かう道(東西)の中間であり、
また、塩田城からの善光寺道(南北)との交叉点にあり、
塩田盆地の中心にある。
本殿には煌びやかに、「東六條藤」の紋が飾られていた。
神楽殿には、「立梶の葉」が付いていた。
祭神の鹽垂津彦命は白鳳元年(672)、出雲より分祀とも、
宝亀年中(770ー780)の奉斎とも伝えられる古社。
白鳳当時、百済の帰化人が東国へ送られ、
平安時代初期、小県郡の帰化人に姓を賜るという史実から、
帰化人によって米作が発達し、信濃の中心と発達する基に
なったと考えられる。
周囲には、口明塚古墳・冨士塚古墳などがある。
式内社・鹽野神社の論社だが、
当社の他に、前山の塩野神社も論社となっている。
宝暦七年、両社で論争が起り、寺社奉行の裁断で、
両社とも塩野神社の社名使用を停止された。
その後、当社を北鹽野神社、前山を南鹽野神社とし、
争いを起こさない事を誓った。
現在の郷土史家の判断では、当社が有力であるが、
その中で『上田史』を執筆した藤澤直枝の言葉が印象的だ。
「現在の姿でその神社の新古正否をきめることは危険である。」
宝暦以前は、前山の社を大宮、当社・保野の社を大明神と区別していたらしい。
配祀の素盞鳴命は、永禄年間に領主武田信玄によって京都祇園社より勧請。
健御名方命は、元禄十五年に勧請された。
黄色い鳥居から、緩やかに参道を登ると、
廻り舞台を供えた直来殿がある。
その向かいに拝殿があり、左手に神楽殿。
右手には境内社が多く並んでいる。
盆地の中心部にあるため、周囲に山はなく、
境内の樹木も疎らな印象だが、
廻り舞台や境内社の多さから地元の信仰の篤さは感じられる。。
黄色の鳥居  | 参道  |
境内 |
 |
廻り舞台のある直来殿 板で閉じられている  | 社殿  |
平成十二年参拝当時の廻り舞台 |
 |
拝殿  | 本殿  |
本殿右手に並ぶ境内社 皇大神宮、蠶影神社、鼠除韓猫明神、白山神社など |
 |
|
鹽野神社は式内社小縣郡五座の内三座の
小社の一に挙げられているが、前山と保野に同名の社があ
り、現在は共に延喜式内鹽野神社を名乗っている。宝暦七
年(一七五七)から明和三年(一七六六)まで一○年間に亘
り、共に延喜式内社を主張して社号の大論争が続き、遂に
幕府の寺社奉行の裁きを受けることになり、その結果共に
証拠不十分の理由で、南社とも社号を停止されることにな
り、保野神主保屋野日向と前山神主宮澤大膳が和談し、済
ロ証文を奉行宛差出している。その結論に保野は北鹽野神
社、前山は南鹽野神社と祝称して睦まじくやって行くとい
うことを誓っている。その後、未だにどちらが真の鹽野神
社かは郷土史研究家も解明できないでいる。 明治以来当地方の郷土史の二大家と言はれる上野尚志、 藤澤直枝はともに保野は福田郷(和名類聚抄)に属し、上田 盆地における稲作創始の二大地帯の一であり、そこに現存 する口明塚古境とともに福田郷の古社であることを主張さ れた。上野尚志著『信濃國小縣郡年表』は今も上小郷土研 究会によって復刻されて、郷土史愛好家に使用されている が、氏は保野が式内社であることを断言している。しかし 今もなおかっての寺社奉行の裁定に従ふべきであろうと考へる。 鹽野神社は宝暦七年(一七五七)前山と保野の神 主が社号論争をはじめるまでは、前山は大宮、保野は大明 神(棟札による)と称していたことは明らかであるが、長 い間双方とも鹽野神社とは氏子も言わなかったことがわか る。従って由緒なども主として論争時の言い分として言い はじめたものが多いとも思はれ、伝承は余り信用できない ものとなってしまった観がある。それよりも明治以来の郷 土史家の研究の方が地方民からも信頼を受けている。特に 有名な上野尚志はその著『信濃國小縣郡年表』に「前山村 の方は証書一○数通あれども皆後世の偽作にして一も取る に足るものなし」と言いきっているし、『上田市史』を執 筆した藤澤直枝も「現在の姿でその神社の新古正否をき めることは危険である。鹽野神社の場合保野は福田郷であ り、前山は安曾郷であり、福田郷には保野の鹽野神社以外 に然るべき神社のないことに注目する方が大事だ」と説い ている。 −『式内社調査報告』− |