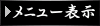[HOME] >
[神社記憶] >
[北陸地方] > [HOME] >
[神社記憶] >
[北陸地方] >
|
|
|
二上射水神社
ふたがみいみずじんじゃ
富山県高岡市二上1519

|
||
富山県高岡市にある。
高岡駅の北3Kmほどの、二上山の南麓に鎮座。
境内入口には、朱の鳥居が立ち、参道がまっすぐ北へ延びている。
参道を歩くと、左手に三本杉。
当社の特殊神事である「築山」はここに築かれる。
三本杉の奥には、天の真名井。
参道を歩き、数段の階段を登ると明るく広い境内。
正面に社殿があり、左手には資料館と築山収蔵庫。
収蔵庫の中を覗くと、築山を見ることができる。
社殿の左隣りには、御神像を納めた、コンクリートの庫。
鎮座の年月日・由緒は不詳。
社伝によれば、養老元年、僧行基により養老寺が建立された。
また、続日本紀には、宝亀11年に従五位下の神階を得たとある。
延喜式・出雲本では、当社・射水神社が名神大社となっており、
現在、最古の写本とされている九条家本では、
気多神社が名神大社となっている。
が、気多神社の神階昇授に関しては国史には見られない。
『白山記』には「二神がもと一宮であったが、
新気多が之を争い、二神が力なくして新気多に一宮をとられた」
と記されているらしく、名神大社の変化は、
勢力争いとその移動の影響だろうと見られている。
明治になって國幣中社に列せられたが、
社僧の影響下にあり、神社であるか寺院であるかの区別もつかず、
養老寺の境内末社的有様であったため、
聖地二上を捨てて高岡城跡へ遷座した。
しかし、二上村の氏子の反対にあい、
古社地(現在地)にも、分社が残され、戦後独立して越中総社射水神社となった。
この顛末にも、勢力争いの影を見ることができる。
ちなみに、高岡城跡の射水神社は、越中総鎮守射水神社と称している。
祭神・二上神に関しては諸説ある。
・瓊々杵尊
・武内宿禰
・武内宿禰の孫、大河音足尼(伊彌頭国造の祖)
・天二上命(天村雲命の別名)
・大己貴命
特殊神事「築山」に関しては、下記の案内を見て欲しいが、
「院内わりこみ」が何を意味した動作なのだろうか。
いろいろと想像してみると面白い。
神紋は社殿や神馬像についていた梅鉢。
ただし、これは前田家の影響によるものだろう。
築山収蔵庫にある築山には、楓のような紋が付いていた。
天狗に関係する葉なのかもしれない。
参道横の三本杉  | 参道  | 社殿  |
天乃真名井  | 手水  |
拝殿 |
 |
御神像庫  | 本殿  |
境内の二上資料館と築山収蔵庫  | 収蔵庫の中の築山  |
|
富山県指定無形民俗文化財
二上射水神社の築山行事
昭和五十七年一月十八日指定
古代信仰では、神は天上にあり、祭に際して降臨を願うも
のとされた。この行事は毎年四月二十三日二上射水神社の春祭に行
なわれる。境内の三本杉と呼ばれる大杉の前に、社殿に向って築かれる臨
時の祭壇は、幅四間、奥行三間、上下二段になっており、上段中央に唐破
風の簡素な祠が置かれ、その前に日吉、二上大神、院内社三神の御霊
代である御幣が立てられる。屋根の上には斧をかざした天狗が立ち下段に
は甲冑に身を固めた四天王の藁人形が置かれ、祭壇のまわりは造花
で飾られる。祭礼の前日の夕刻、頭屋にあたる山森氏(御幣ドン)と神主が二 上山頂にある奥の御前の日吉社から御幣に神を迎える。一夜自宅で お護りし翌日築山に移す。院内社は祭の当日迎えられる。 祭儀は、午後二時から行なわれ社殿で例大祭の儀式が済むと三基の 神輿が巡行する。ゲンダイジンを露払いに、御幣ドン、神主が続き その後院内社、二上大神、日吉社の神輿が続く、途中で院内社の神輿 だけが一旦鳥居の外に出て、戻って二上大神と日吉社の間に割って入る。これを 「院内わりこみ」という。その後、築山の前と天の真名井の前で祝詞が奏上さ れ、本殿の前に戻って儀式が終る。祭儀が終ると築山はただちに解体され 片付けられる。遅れると神様が荒れるという。 この行事は、天上から臨時の祭壇に神を迎える古代信仰を本義を良 く残している。又動かぬ築山がやがて動く曳山へと発展していったと考えられており 高岡御車山の原初形態を知る上でも貴重である。又社殿の神事と 古代信仰の築山神事の二重の神事を同日に行なっている点も興味深い。 −境内案内− |
二上射水神社には、古来、二上山に摂社四社が存在していたが、
今は、高岡城跡の射水神社の管理になっているらしい。
二上山山頂第一の峰には「奥の御前」と称する日吉社(大山咋命)。
山頂から少し南の第二の峰には「前の御前」と称する悪王子社(地主神 )。
二上山南麓の東側の二上院内には「院内の宮」と称する院内社(菊理媛命)。
二上山南麓の西側には諏訪社(建御名方命)。
悪王子社の祭神は不詳だが、二上神の分身とされ、
昔、越中一円から十五歳以上の娘を人身御供として要求していた悪神。
天正天皇に派遣された行基が、お経を唱えると大蛇と化して出現し
さらにお経を唱えると降参して、山の守り神となることを約束したという。
二上山山頂 奥の御前 日吉社  | 前の御前 悪王子社  |
二上山前面、西の麓 諏訪社  | 二上院内 院内社  |