 [HOME] >
[神社記憶] >
[四国地方] > [HOME] >
[神社記憶] >
[四国地方] >
|
|
|
深淵神社
ふかぶちじんじゃ
高知県香南市野市町西野1202

|
||
式内社 土佐國香美郡 深淵神社 |
高知県香美郡野市町(現香南市)。
高知市街から55号線を東へ向い、
南国市を過ぎて、物部川を渡ると野市町に入る。
55号線から北上して1Km程の道路脇にある。
境内側面が道路に面しており、
境内入口は、道路から少し東へ入ったところ。
境内は、ガランとして何もない印象だったが、
社殿は、大きく立派。
本殿は、完全に覆われていて確認できなかったが、
『神社名鑑』では清和造とあった。
祭神・深淵水夜禮花命は、古事記に登場する神。
素盞嗚尊の曾孫にあたり、大国主命の曾祖母になる。
ちょうど、素盞嗚尊と大国主命の中間に位置する神。
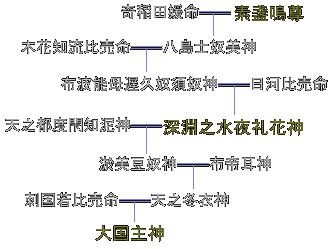
境内は、物部川の河口部東岸にあり、祭神はこの川の神だと思う。
当地の土地神が、古事記の重要な場所に組み込まれているのは
大変興味深い話だ。出雲と、深い関連があるのかもしれない。
あるいは、深淵水夜禮花命は、出雲の神で、
当地名・深淵との類似から、付会された可能性もあるのではないだろうか。
昔は、物部川の場所にあったが、洪水で川底に沈み、
十禅寺に遷座した。よって十禅寺権現とも呼ばれるが、
その十禅寺も洪水で流れたため、現社地に移った。
川の神の社が、再三流れるのも、面白い。
『香美郡志』には、「夜禮」は「破れ」、「花」は「端」の意味であり、
「深淵水夜禮花命」とは、深淵の水(物部川)の氾濫時に、
その被害を食い止める神であるという。
県社列格は、明治十二年。十禅寺からの遷宮は明治二十五年。
ということは、十禅寺にあったころ、県社に指定されたことになる。
どうりで、現社殿・境内は、県社としては小規模なのだ。
神紋は、社殿の幕にあったものだが、謂われは不明だ。
境内入口の白木鳥居  | 境内の白木鳥居  |
境内 |
 |
社殿  | 社殿扁額  |
境内 |
 |
|
祭神 深淵水夜禮花命
創立年代詳かならず、古老の博説に拠るに、孝安天皇三十一年、神勅ありて曰く我此地に居ること久し、我は
深淵の水夜禮花命なりと言畢りて御身を隠くされたるにより、萬民深淵の神なりと崇め奉斎したるなりと
祭神は古事記に出てたる神にして、深淵は和名鈔郷名部に土佐香美郡深淵、古事記云布波能母遅久奴須奴神娶女二
日河比賣一、生二子深淵之水夜禮花神一とありて深淵之水は母の御名河に由あるものならんか、三代実録に清和天
皇貞観十二年三月五日此神に従五位下を授けられ、又陽成天皇元慶三年九月廿七日従五位上を授けられ、延
喜の制式内小社に列せり、式社考に「此社今在二野市一里人為二十禅師一、舊祠嘗在二深淵村一、地広樹老尤可二凝信一、寛永
中前国宰大墾二辟鏡野一、潅漑之利被二数千町一、於レ是河水失二古道一数流合併為レ一、一旦洪水壊嚢、社地為レ所二潰決一、巨
木恠厳今猶在二河底一見在小社、四十年前里民徒造レ之と(按ずるに四十年前とあるは寛永年中に当るなり)古来より佐太郷の總鎮守にして、
曾て深淵権現、十禅神権現と称したるを、明治元年深淵神社と改め、同五年郷社に列し、同十二年九月三十日
縣社に昇格せり。本殿、拝殿、御炊殿等の建物を備へ、境内地百八十一坪(官有地第一種)を有せり。 −『明治神社誌料』− |
【 深淵神社 】







