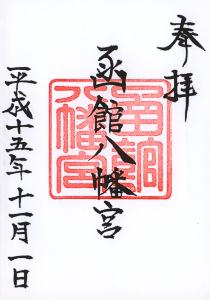[HOME] >
[神社記憶] >
[北海道東北地方] > [HOME] >
[神社記憶] >
[北海道東北地方] >
|
|
|
函館八幡宮
はこだてはちまんぐう
北海道函館市谷地頭町2−5

|
|||
|
旧國幣中社 |
北海道函館市にある。
市電・谷地頭線の最終駅谷地頭駅から西へ500m。
函館山の南東麓に鎮座。
谷地頭えきから延びた参道に、大きな鳥居が見えている。
境内は東向き。
参道の階段を登ると正面に美しい社殿。
紅葉の函館山を見上げる位置。
境内左手には境内社の鶴若稲荷社がある。
参拝は十一月の初め。
北海道に到着して、まずここを訪れた。
当社の背後、函館山の麓を、ハイキングのコースが設けられているので、
秋の森林を歩いて散策。
文安2年(1445)、函館が「宇須岸」と呼ばれていた頃、
領主河野加賀守政道が築城し、館の東南の隅に
八幡社を立てたのが当社の創祀。
その後、永正9年(1512)蝦夷の戦で滅亡し、
一族は、赤川村に移動したため、当宮も遷座していたが、
慶安年間に元の地に戻り、文化年間に社殿を造営。
明治になり、北海道開拓使の崇敬社となる。
現社殿は、大正7年に完成したもの。
旧国幣中社。
一之鳥居 |
 |
境内入口 |
 |
鳥居  | 参道の鳥居  |
参道  | 拝殿  |
社殿 |
 |
鶴若稲荷神社  | 本殿  |
大正から昭和にかけて活躍した鳥瞰図絵師 吉田初三郎の 「函館八幡宮」 |
 |
|
文安2年(1445年)河野政通が蝦夷地に渡来し現在の元町公園通りに館を築いたとき、その東南のすみに八幡社を立てたのが始まりといわれ、この八幡社は、一時赤川村(現市内赤川町)に移ったが、慶安年間(1648−1651年)に再びもとの地に移した。 寛政11年(1799年)幕府の東蝦夷地直轄にあたり、蝦夷奉行(後に箱館奉行と改め、翌年、奉行所庁舎が完成した。)が置かれることとなり、八幡社がある河野館跡地を奉行所用地としたため、文化元年(1804年)会所町(現八幡坂の上)に移された。 その後、明治11年(1878年)の大火で社殿を焼失し、翌年12年にも仮殿が焼失したため、同13年(1880年)この地に移った。 大正7年(1918年)に完成した現在の社殿は、鎌倉時代に発達した聖亭造りを加味し、新様式も取り入れた八幡造りであり、優雅で壮麗な建物である。 −『平成祭データ』− |
境内の左手の道を南へ300mほど歩くと、
箱館戦争で戦死した土方歳三や中島三郎父子など、
旧幕府軍戦死者800人の霊を祀る、「碧血碑」がある。
碧血とは、
「義に殉じて流した武人の血は三年たつと碧色になる」
という中国の古事によるもの。
碧血碑から北へ延びる森林の中の小道を進むと、
函館山東麓のロープウェイ乗り場方面へ出る。
函館八幡宮の神域の背後を通る宮の森の小道で、
1.2Kmの短い距離だが、なかなか気持ちの良い道。
函館は、函館山から函館港へ下りる地形のため、坂の多い街。
幾つかの有名な坂があるが、なかでも有名な八幡坂。
文化元年(1804)に箱館奉行所の拡張工事により、
この坂の上に函館八幡宮が遷座された。
明治11年(1878)の火災で焼失し、
明治13年、現在地に遷座したが、八幡坂の名はそのまま。
観光客がカメラを構えて撮影していたので、僕も撮影。
碧血碑 |
 |
碧血碑から延びる 宮の森の小道  | 上から八幡坂 函館港を見下ろす  | 下から八幡坂 函館山を見上げる  |