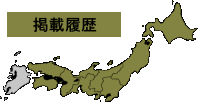[HOME] >
[神社記憶] >
[九州地方] > [HOME] >
[神社記憶] >
[九州地方] >
|
|
|
沖縄神社
おきなわじんじゃ
沖縄県那覇市首里鳥堀町1

|
|
旧県社 |
沖縄県那覇市にある。
首里城の東1Kmの弁ケ嶽に鎮座。
モノレール首里駅から500mの丘の上。
小さなコンクリートの祠があり、
中に5つの石碑が並ぶ。
創立は大正14年と新しい。
沖縄王統の祖・舜天王を祀る神社。
創立時は首里城を境内とし、首里城正殿を拝殿としていたが、
戦争で破壊された。
後、現在の弁ケ嶽小嶽に再建されたらしい。
祭神に関しては、『平成祭データ』には、
舜天王、舜天王の父・源爲朝、中興の祖・尚圓王などが記されていたが、
祠内部には、以下の五王の名があった。
舜天王・英祖王・察度王・尚思紹王・尚圓王。
舜天王は、1187年に即位した沖縄王統の祖で、三代続いた。
その後、英祖王が王位を継ぎ、四代続く。
後、察度王(二代)、尚思紹王(七代)、尚圓王(十九代)
と王位が移動し、明治維新となる。
境内社殿 |
 |
祠内の石碑 |
 |
|
沖縄神社
那覇市首里當蔵町鎮座、祭神、舜天王、尚圓王、尚敬王、尚泰王、源為朝公、例大祭、十月二十日 由緒 県民の熱烈な敬神崇祖の念から大正十一年十二月、県社沖縄神社創立の議が起こった。祭神は県民に最も由縁の深い國祖舜天王、又その後四百年間に功績のあった中興の國王尚圓王及び本県の文化事業に貢献した英主尚敬王更に明治維新の宏謨によって県民の向ふところを定めた最後の國主尚泰王を主神として報本反始の意から舜天王の父君源為朝公を配祀することゝした。敷地は舜天王以来七百年間本県政治の中心地であった首里城を選定し、大正十二年三月三十一日創立を許可せられ、創立奉賛会を組織し、県下一般より募金した、同年九月起工、同十四年一月竣工、同十五年十月二十日県社に昇格した。同十一月二日神饌幣帛料を供進する神社に指定せらる。昭和十九年十月戦災焼失、戦後、有志により再建期成会を結成し、昭和三十七年より那覇市首里鳥堀町弁ケ嶽小嶽の市有地を貸借し境内地とし、小祠を設け祭祀を続けている。昭和六十三年十一月、本殿と玉垣の補修工事竣工。 −『平成祭データ』− |
現在地である弁ケ嶽は住宅地の中にある大きな丘だが、
二つの丘からなり、東側を大嶽、西側を小嶽と呼ぶ。
祠があるのは小嶽の方。
大嶽の前にはコンクリートの門がある。
閉まっていたので中には入らなかったが、小道が奥に続いていた。
弁ケ嶽自体が御神体として信仰されていたようだ。
弁ケ嶽門  | 大嶽  |
|
弁ケ嶽
また、かつては石門の前に、拝殿と呼ばれる建物がありました。 −案内板より− |
観光名所になっている首里城は、
沖縄神社として国宝に指定されていた。
守礼門  | 奉神門  |
正殿 |
 |
【 沖縄神社 】