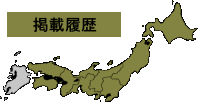[HOME] >
[神社記憶] >
[九州地方] > [HOME] >
[神社記憶] >
[九州地方] >
|
|
|
興神社
こうじんじゃ
長崎県壱岐市芦辺町湯岳興触676

|
||
式内社 壹岐嶋石田郡 天手長男神社 名神大 |
壱岐の中央部、382号線から芦辺へ抜ける道の途中にある。
芦辺方面へ向って左手に白い鳥居があり、鳥居前は駐車スペース。
延宝四年(1676)、式内社調査の際、
平戸藩の国学者橘三喜は、当社を式内・與神社に比定したが、
與の字を興と見たための誤りとされている。
興神社の「興」は、「国府」の意味であり、
近くに壱岐国府があった場所で一宮でもあった。
当社の摂社には、壱岐総社神社も存在する。
ということで、式内・天手長男神社ではないかと思われる。
祭神に、息長足姫尊(おきながたらしひめのみこと)が含まれている。
神功皇后の別名なのだが、字面だけを見ると、
壱岐の足長姫と見ることもできないだろうか。
すると、足仲彦尊(仲哀天皇)が、天手長男となるだろう。
あるいは、天手長男・天手長比売は、神功皇后の一族であるのかもしれない。
壱岐七社参拝の一社。
七社とは、白沙八幡・興神社・住吉神社・本宮八幡・箱崎八幡・国片主神社・聖母宮。
印鑰大明神とも、当国一之宮とも呼ばれた古社。
『宗像大菩薩御縁起』によると、神功皇后の三韓征伐に際して、
宗大臣(ムナカタの神)が奮戦して武勲を輝かしたという。
その時、宗大臣は『御手長』を捧げ来り、これに武内宿禰の織り持てる
赤白二流の旗を付けて、軍の前陣で『御手長』を振り下げ、振り上げ
して敵を翻弄し、最後にこの『御手長』を息御嶋(オキノシマ)に立てた。
この息御嶋は宗像の沖ノ島であり、そして『御手長』については、
「異國征伐御旗杆也」とある。
これが壱岐島の「天手長男神社」「天手長比賣神社」の『天手長』の由来。
そして武内宿禰がこの「御旗杆」に付けられた「赤白二流之旗」を
織ったので、織旗の神が祀られ、織幡神社の社記によると、
「壱岐真根子臣の子孫の人つたへて是を祭る」とあり、
織幡神社の社家は壱岐氏である。
道路に面した鳥居は新しいようだ。
境内もそれほど広くはないが、木漏れ日の参道と
参道に残る鳥居が往時を偲ばせる雰囲気。
当社の摂社である総社神社の場所がわからず、周囲をうろついた後、
社前の家の方が通りかかったので、聞いてみた。
当社の氏子の方で、これから例祭日の打ち合わせがあるそうだ。
参拝日が3月31日、例祭日は4月13日で2週間前だ。
忙しい時なのだが、わざわざ近くの家の方にも聞いていただき、
場所を丁寧に教えていただいた。
「案内したいけど、これから打ち合わせだから申訳ない」
そう言って見送っていただいた。
境内入口 |
 |
参道  | 参道の鳥居  |
境内の境内社  | 参道を振り返る  | 参道奥に社殿  |
境内 |
 |
社殿  | 後方の本殿覆屋  | 本殿  |
|
興神社 由緒沿革 主祭神 足仲彦尊,息長足姫尊 相殿 應神天皇、仁徳天皇、天手力男命、八意思兼神、住吉大神 例祭日 四月十三日 神幸式大神楽奉奏 由緒沿革
−境内案内− 興神社位置 芦辺町湯岳興触 祭神 大鷦鷯天皇、息長帯姫尊、誉田別天皇、帯仲彦天皇、天手力男命、八意思兼神、住吉大神 現宮司 品川堅磐(代務) 由緒 『神社明細帖』に「興神社、旧平戸藩別段崇敬七社ノー也、但式内氏子アリ」「勧請年暦不詳一説嵯蛾 天皇弘仁二年辛卯(八一一)冬十月一日鎮座奉ル云々延宝調前国府社トモ印鑰大明神トモ称。社地二反八畝十二 歩、但無税。造営民費、白銀七枚平戸藩寄附金国中民費。「攝社一社総社神社」、『壱岐国神社田畑帳』に「興神 社、宗廟、社領高二石祭米六舛六合、定祭八月十三日御代参有り」と記している。 永禄九年(一五六六)二月松浦隆信押字の棟札「上棟龔奉再興印鑰大明神御宝殿一宇」や慶安二年(一六四九) 八月松浦鎮信押字の棟札「上棟奉造営壱岐郡印鑰大明神御宝殿一宇」にも見られるように、印鑰大明神と呼ば れ、また当国一ノ宮(神社帳)とも言われており、興神社とは呼ばない。延喜式巻十の壱岐島二四座の中に名神小 「與神社」があり、「延宝年中式社改の時、与神社を興神社と心得、興といふ地名によりて、印鑰大明神を興神 社」(『名勝図誌』)と誤ったと思われる。『壱岐神社誌』も「当社創建の際より延喜式に登録され給ひし頃までは 天手長男神社と称せしが後に佛説の習令の為に国衛の印鑰保管等の関係によりて印鑰大明神と唱へ奉り又一面に は国府所在のために国府宮とも呼び来りて延宝四年査定の時本来の天手長男神社の称呼が廃れて社号を伝へざる ために遂に過りて当社を以て式内小神與神社なるべしとして遂に興神社と決定し天手長男神社は新に物部村に勧 請するに到れるものなりといふに帰著す。然れども其一の宮なる通称は今にこれを存し、又大七社の崇敬は明治 維新後廃藩と共に止みたりと雖、民間に於ける大七社の信仰は更に衰ふる所なし云々」としている。社殿造営ご とに国主より白銀七枚の寄進を受けていることからも、それは明らかである。 明治九年(一八七六)十二月村社となり、明治四十年七月には神饌幣帛料供進神社に指定された。例祭は四月 十三日。 −『芦辺町史』− | ||||||||||||||||||||||