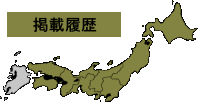[HOME] >
[神社記憶] >
[九州地方] > [HOME] >
[神社記憶] >
[九州地方] >
|
|
|
爾自神社
にじじんじゃ
長崎県壱岐市郷ノ浦町有安触997

|
||
式内社 壹岐嶋石田郡 爾自神社 |
長崎県の壱岐、郷ノ浦にある。
郷ノ浦の西側、半城湾の北にある有安触の山中。
周囲の道は、整備されかなり広く、
手持ちの地図とかなり異なっていた。
59号線から一本逸れた狭い道を登っていく。
境内に入って参拝中、頭上で鳥の大群の声。
見上げると、鶴の大群だった。
弧を描き、矢印状になって飛び回っていた。
壱岐を経由地として、北へ戻る途中だったんだろうか。
はじめて見たので、しばし感動した。
桜の参道を歩くと、拝殿・本殿がある。
本殿は覆われているが、後方に「東風石」がある。
頭上で乱舞する鶴の大群を見ながらの参拝。

創祀年代は不詳。
式内社・爾自神社に比定された神社。
当社は、古号「東風大明神」と云われ、
神功皇后三韓征伐の折り、この石に祈願し、
東風が吹き、無事、三韓へ渡ったという。
聖母神社の神領にあり、西の峰に鎮座したことから
「にじ」神社と呼ぶ。
社殿右に鳥居があり、後方に3m程の石がある。
神功皇后が祈願した時に、2つに割れたということだが、
中央部にヒビが入っている。
大正五年八月、周囲の無格社を合祀した。
大神宮神社 (天照大神,栲幡千々姫命,天手力男命)
禰宜山神社 (御食津神)、立石神社 (石野姫命)
神坂神社 (不明)、國片神社 (少彦名神)
鳥居  | 参道に桜  | 参道  |
拝殿  | 拝殿内部  |
本殿 |
 |
本殿  | 本殿後ろの東風石  |
東風石 |
 |
|
町指定/有形民俗文化財 爾自神社の東風石と石燈籠 所在地 壱岐郡郷ノ浦町有安触997
鎖国政策がとられていた江戸時代に、李氏朝鮮は日本にと
って唯一の修好国であった。日本からまた朝鮮からの使節が
往来し、友好関係を保った。なかでも将軍の代替りの度に慶
賀の使節として来朝した、朝鮮通信使は有名で、三百人から
五百人に及ぶ使節団の一行は、慶長十二年(一六〇七)以降、
前後十二回訪れている。爾自神社 指 定 昭和 五十二年 三月 十日 この通信使の一行は、江戸までの行き帰りに勝本浦に寄航 し、平戸藩の接待を受けた。この時、海上が時化て勝本浦で の逗留が続くと、藩はそのつど壱岐城代に命じて、当社の東 風石に順風祈願を行わせたことが記録されている。 東風石には、神功皇后伝説があって、皇后が三韓出兵の折 り、勝本浦に寄航するが、追い風が吹かないため、この石に 順風祈願をすると、石は二つに割れてさわやかな東風が吹き 出し、出船できたというものである。平戸藩はこの故事にな らったのである。 東風石の大きさは、縦約三・九〇メートル、横約三・三五 メートル、高さ約二・七〇メートル、周囲約一一・四五メー トル。 なお、二基の石燈籠には、寛文十一年(一六七一)十一月吉 日の銘があり、寄進者は講中十五人とある。 −境内案内− |
【 爾自神社 】