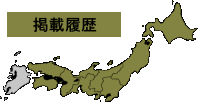[HOME] >
[神社記憶] >
[九州地方] > [HOME] >
[神社記憶] >
[九州地方] >
|
|
|
霹靂神社
いかづちじんじゃ
長崎県対馬市上対馬町大増1073

|
|||
長崎県対馬市にある。
上対馬の東側にある舟志湾の奥、
海に突き出た場所(朝日山)に鎮座。
西側の道路に境内入口の鳥居が建っており
海の方へ参道を進むと境内。
境内全体が、東の海を向いており、入口は裏口。
海に面して、石の鳥居が建っている。
が、鳥居が海に近く正面からの撮影困難。
倉庫のような拝殿の裏に階段があり、上に本殿がある。
本殿の裏に、朝日山古墳がある。
社号の霹靂は、『式内社調査報告』では「いかづち」。
『平成祭データ』には「へきれき」と記されている。
式内社・能理刀神社の論社の一つ。
熊野三所権現とも称しており、
昔、熊野権現が船に乗って渡って来たといい、
多くの懸佛が奉納された古社である。
神社明細帳に「神功皇后の時、雷大臣・安曇磯武良を新羅に遣わし、
雷大臣彼地で女を娶り一男を産む。名を日本大臣と云う。
新羅より帰り給う時、浜久須へ上り給う古跡なり。」とある。
雷大臣は、卜部の祖神。
中臣烏賊津使主(いかつおみ)と同一人物と思われ、
天児屋根命の裔。
神功皇后の時に朝鮮に往来し、神とも人ともつかぬ存在であった。
安曇磯武良は、安曇磯良とも呼ばれ、
神功皇后の水先案内をした人物で、
雷大臣同様、神とも人ともつかぬ存在であった。
境内入口  | 参道  |
海に面した鳥居 |
 |
海に面した鳥居  | 拝殿  |
拝殿後方の階段  | 上に本殿  |
朝日山古墳 |
 |
|
町指定史跡 朝日山古墳郡
1.指定年月日 昭和49年2月1日2.指定地 上対馬町大字大増1073番地 3.説明 この椎の古木が生い繁った丘の上に霹靂神社がありこの丘は俗に朝日山と呼ばれている。本殿の裏側に石室墓の群集があり昔盗掘をうけている。 昭和23年調査が行われ漢武鏡一面・勾玉・鉄製剣・刀・斧・鎌・鋤・紡鐘車・釘・須恵器・土師器が出土した。 この古墳の須恵器はわが国の祝部土器の中で最も古い形式とされている。 九州の祝部土器の形式を分類してその編年をつくる研究の動機となったのがこの朝日山の古式祝部であった。 また金海式土器が学界で問題になったのもこの朝日山出土器が知られてからである。 考古学上朝日山古墳を標準として中期古墳と後期古墳と類別している。 −境内説明− |
【 霹靂神社 】