 [HOME] >
[神社記憶] >
[北陸地方] > [HOME] >
[神社記憶] >
[北陸地方] >
|
|
|
楢本神社
ならもとじんじゃ
石川県白山市上柏野町イ89

|
||
式内社 加賀國石川郡 楢本神社 |
石川県白山市上柏野。
JR加賀笠間駅から、南東に2Kmの町中に鎮座。
国道8号線の南側、路地の奥にある。
拝殿前には、「産の樹(うんのき)」と呼ばれる立派な欅の神木があり、
白山市指定文化財となっている。
楢本神社の論社は、三社あり、距離も近い。
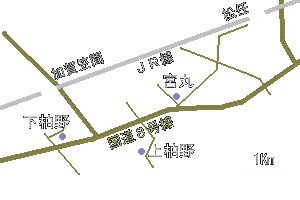
明治には論争があり、特に下柏野と宮丸は、激しく争った。
困惑した石川県は、占いによって神慮を伺うこととしたそうだ。
現在は、数Km南を流れている大河・手取川だが、
昔、このあたりは、その流域地帯であったらしく、
度々の氾濫によって、町々の離散廃滅が甚だしかった。
そういう事情によって、楢本神社も遷座・分祀を繰り返し、
複数の論社が生まれることになったのだろう。
創祀年代は不詳。
当社は、昔、乙剣社と称していたが、
明治になって、楢本神社と改称し、式内論争に加わった。
(『石川縣神社誌』では、明治まで舘社と称していたとある。)
社殿の横に、昔の鬼瓦が置いてあり、丸に巴紋がついていた。
神紋かどうかは、未確認。
鳥居と注連縄を見て、なぜか「カッコいい」と思った。
境内 |
 |
拝殿  | 瓦に巴紋  |
鳥居扁額  | 拝殿前に「産の樹」  | 本殿覆屋  |
|
楢本神社由緒
村社にして創立年代明らかでない。初め乙剣社と呼ぶが
明治十四年に楢本神社を再建する。明治三十九年十二月二
十九日神饌幣帛供進神社に指定された。社記に祭神は御膳氏の祖比古伊邪許志別命と云う説があ るが確証は見当らない。 社伝によると往古は御饌社と名付け、大社にして社地広 大、御供物準備する建物と接続し、老楢・古柏密林をなし て社域を守る。当社は延喜式神名帳記載の旧社(式内社) としても、近郷の住民に大変尊敬されていた。寿永二年後 鳥羽天皇時代(八百二年前)に、手取川大洪水となり、社 殿ことごとく流出し、現在地に移された。 口伝えでは往古御膳氏の遠祖屋主思命の孫、市入命国造 としてこの地に居住し、当社に奉仕、後に訳があって僧と なり宝山院と名乗る。代々当社の社僧を務める。そして御 膳の榊葉を諸国に神社に納めたといわれる。現在御膳の館 という地はその居館のあった所ではいかと思われる。 解説
−境内案内− |
【 楢本神社 (上柏野) 】







