 [HOME] >
[神社記憶] >
[関西地方] > [HOME] >
[神社記憶] >
[関西地方] >
|
|
|
賀茂別雷神社
かもわけいかづちじんじゃ
京都府京都市北区上賀茂本山339
境内には末社・摂社が多い。とりあえず目に付いたものは全部撮影したが、
抜けがあったようだ。かなり念入りに参拝したつもりなのに....
境内は広く芝生に覆われている。
境内右手、その芝生横を流れる御手洗川(ならの小川)沿いに、末社が並ぶ。
境内右手、御手洗川の側に末社・梶田社。
祭神は瀬織津姫神、祓戸四柱の一神。川瀬の女神。
お祓いの神で、ここでお祓いをして本社へ参拝したという。
梶田社の北に末社・山森社(山ノ森神)。
祭神は素盞嗚神・稲田姫命・田心姫命。疫病を祓うらしい。
鎮座年代は不詳。
式内社・鴨岡太神社の論社であり式内社・賀茂山口神社の論社でもある。
元は賀茂川の西、西賀茂山ノ森に鎮座していたらしい。
貴布禰神社が流れてきたという伝承がある。
山森社の北に、奈良鳥居が立ち、庁屋(北神饌所)がある。
庁屋を拝殿として、摂社・奈良神社がある。
鎮座年代は不詳。祭神は奈良刀自神。サバの神。
神饌(神の食事)を司る神らしい。
末社梶田社 瀬織津姫神  | 末社山森社 素戔嗚神、奇稻田姫神、田心姫神 式内論社・賀茂山口神社・鴨岡太神社  |
奈良鳥居と庁屋と摂社奈良神社 奈良刀自神 | |
 |  |
奈良神社の北に、曲水の宴が開催された渉渓園がある。
渉渓園の側に第五摂社・賀茂山口神社。別名沢田社。
創祀年代は不詳。
式内社・賀茂山口神社の論社。
古来賀茂別雷神社の第七摂社だったが、
明治十年三月二十一日に第五摂社に定められた。
祭神は御歳神。本社および神領地の田畑の守護神。
ただし、倉稲魂命、太玉命、経津主神などの異説がある。
賀茂山口神社に東に、丘の上に登る参道があり、朱の鳥居が並んでいた。
丘の上には、二葉姫稲荷、天之斑駒神社、金毘羅、八嶋龍神。
他の末社・摂社には祭神などの説明があるが、ここにはない。
賀茂山口神社の西、岩の上に末社・岩本社。祭神は住吉三神。
曲水の宴が開催された渉渓園 |
 |
摂社賀茂山口神社 御歳神 式内論社・賀茂山口神社  | 境内右手、 二葉姫稲荷等への参道鳥居  |
末社岩本社 住吉三神 |
 |
授与所の奥、樟橋の側に末社・橋本社。
祭神は衣通姫神。和歌・芸能の神。
楼門の東、御物忌川という小川の側に、末社・川尾社。
祭神は罔象女神。御物忌川の守護神。
川尾社の側に、伊勢神宮遥拝所。
末社橋本社 衣通姫神  | 橋本社から楼門  |
末社川尾社 罔象女神  | 伊勢神宮遥拝所  |
楼門の南、御物忌川を越えると、摂社・須波神社。
本宮の前庭の守護神で、
祭神は、阿須波神、波比祇神、生井神、福井神、綱長井神。
式内社・須波神社の論社。
昔は諏訪社と称していたが
明治十年三月二十一日に当社の第七摂社に定められ、
須波神社と改められ、祭神も改められた。
須波神社の横に、本宮の第一摂社・片山御子神社。別名片岡社あるいは片山社。
祭神は、玉依比賣命。本宮祭神の母神。
大己貴命や事代主命、別雷神の御子とする異説もある。
式内社・片山御子神社に比定されている。
中門の奥は撮影出来なかったが、本殿の周囲に幾つかの境内社がある。
まず、中門の横には、末社・棚尾社(豊石窓神、櫛石窓神)。門神だろう。
中門の中に、杉尾社(杉尾神)と土師尾社(建玉依比古命)。
本殿の右に若宮神社(若宮神)。
さらに右手に山尾社(大山津見神)と貴布禰新宮神社(高靇神)がある。
本殿周囲の社名は「〜尾社」というのは、何か意味があるのだろうか。
土師尾社は式内社・賀茂波爾神社の論社。
摂社須波神社 阿須波神外四柱 式内論社・須波神社  | 摂社片山御子神社 玉依比賣命 式内論社・片山御子神社  | 末社棚尾社 豊石窓神、櫛石窓神  |
境内の入口付近には、神社前の木の横にあった祠、藤木社(瀬織津姫神)。
神社前の木の横にあった祠、藤木社 瀬織津姫神 | |
 |  |
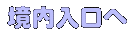 |





